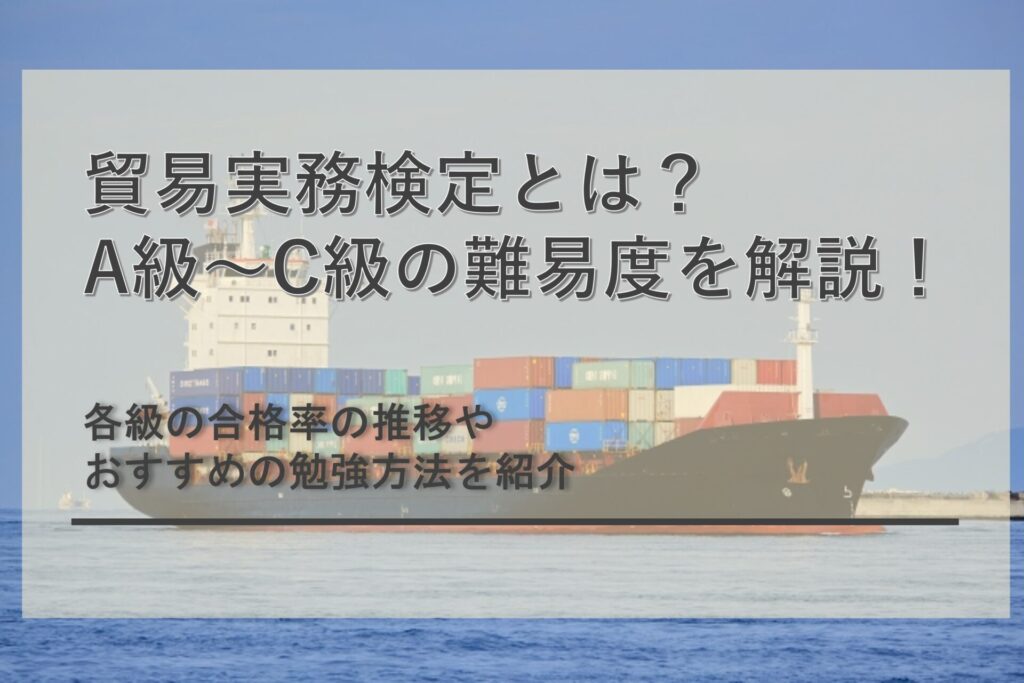貿易国である日本では、年間の輸出入金額の合計は100兆円を超えており、さまざまな物品が輸出入されています。
輸出入の際には正しく申告手続きを行い、税関を通す必要がありますが、そこで依頼主に代わって通関業務を行っているのが通関士です。こうした業務を行えるのは、国家資格である通関士の資格を持った人に限られており、税関業務の専門職としてこれからも高いニーズが見込まれています。
通関士の資格は人気が高いため、資格取得に興味がある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、通関士の難易度や合格率、独学におすすめの勉強法などを解説していきます。
ホワイト企業の求人を探したい人は
転職エージェントの利用がおすすめ!
独自アンケートを基に厳選!
仕事やキャリアに悩みがある人は、
キャリアバディでオンライン相談がおすすめ!
- キャリアの悩みをオンライン相談!
- 相性のいいキャリア専門家を検索可能
- 転職エージェントではないので
フラットな意見を聞ける - キャリア相談広場は無料相談可能!
キャリア相談する専門家を探す
通関士の合格率は?
2023年度の通関士の受験者数は6,332名に対し、合格者数は1,534名で合格率は24.2%でした。
過去10年間の受験者数、合格者数、合格率の推移は下記のとおりです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 6,332名 | 1,534名 | 24.2% |
| 2022年度 | 6,336名 | 1,212名 | 19.1% |
| 2021年度 | 6,961名 | 1,097名 | 15.8% |
| 2020年度 | 6,745名 | 1,140名 | 16.9% |
| 2019年度 | 6,388名 | 878名 | 13.7% |
| 2018年度 | 6,218名 | 905名 | 14.6% |
| 2017年度 | 6,535名 | 1,392名 | 21.3% |
| 2016年度 | 6,997名 | 688名 | 9.8% |
| 2015年度 | 7,578名 | 764名 | 10.1% |
| 2014年度 | 7,692名 | 1,013名 | 13.2% |
過去の合格率の推移を見ると(上記表を参照)、例年10%~15%で推移しており、資格試験の中でも難易度が高いものであることがわかります。
他国家資格の合格率と比較
通関士の合格率は、独占業務を持った他の国家資格の合格率と比較してどうでしょうか。
| 資格名 | 合格率(2023年度) |
|---|---|
| 社会保険労務士 | 6.4% |
| 行政書士 | 14.0% |
| 宅地建物取引士 | 17.2% |
| 通関士 | 24.2% |
| 社会福祉士 | 44.2% |
| 第二種電気工事士 | 58.9% |
通関士よりも合格率が低いのは、社会保険労務士や行政書士といった難関資格です。
宅地建物取引士と通関士は合格率を見ると同程度となっていますが、試験範囲や合格基準を鑑みると一般的には通関士試験の方が必要な勉強時間が長く、取得難易度の高い資格といえるでしょう。
の資格取得難易度はどれくらいなのか?合格率推移から徹底解説-300x200.jpg)

通関士試験の難易度は高い
通関士の例年の合格率は10%~20%ですが、年度によっては10%を切る年もあり、難易度の高い資格といえるでしょう。
ここでは通関士試験の難易度について、以下のポイントについて詳しく解説していきます。
必要な学習時間の目安
通関士試験の合格に必要な学習時間は、400時間程度が目安です。同程度の合格率である宅地建物取引士試験に必要な学習時間が、300時間から400時間といわれていますので、同程度以上の勉強が必要になると考えられます。
ただし通関士の場合は、あまり馴染みのない税関や輸出入に関する知識が求められるため、貿易関連業務の経験がない人の場合は、宅地建物取引士よりも難しく感じる人も多いでしょう。
通関士試験の難易度が高い理由
通関士試験が他の国家資格試験と比べて難易度が高いことがわかりましたが、合格が難しい具体的な理由を詳しく見てみましょう。
貿易関連の法律知識が求められる
通関士試験では、多くの人にとってあまり馴染みがない貿易関連の法律知識が求められます。
初めて聞くような法律用語や税関や輸出入に関する専門用語が頻出するため、実務未経験の人は理解し辛い内容といえるでしょう。
実務試験では最低限の英語力も必要
実務試験では申告書に書かれた英語の内容を理解する必要があります。
品目の名称などは専門的な英単語などが使われることもあり、英語が苦手な人にとってつまずきやすいポイントになります。
出題範囲が広く暗記が必要
試験問題のうち、通関業法と関税法等については出題範囲も広く、暗記することが多い科目です。法律的な知識を問う問題では専門用語をしっかり理解しておく必要もあります。
通関士業務の基礎となる知識ですので、しっかりと身につけておかなければなりません。
通関実務は応用力が問われる
通関実務の試験では、実務的な申告書作成の問題が出題されます。
基礎となる知識は必要ですが、暗記しているだけでは解答できません。また課税価格を算出するなど正確な計算力も求められる問題形式になっています。
法改正にも対応しなければならない
通関士の試験では、受験する年の7月1日現在で施行されている法律・政令・省令などが出題される範囲となります。
毎年のように法改正があるため、対応が必要になります。試験の勉強をしながら、最新の法改正についての情報収集をしておかなければなりません。
通関士試験の概要
通関士試験は毎年1回実施されています。通関士試験の概要について確認しておきましょう。
通関士の試験科目
通関士試験は以下の3科目で実施されます。
| 試験科目 | 配点 | 試験時間 |
|---|---|---|
| 通関業法 | 45点 | 9:30~10:30 |
| 関税法等 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法) | 60点 | 11:00~12:40 |
| 通関実務 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務) | 45点 | 13:50~15:30 |
試験形式
通関士試験の出題形式・配点・出題数は下記のとおりです。
| 試験科目 | 出題形式・配点・出題数 | |||
| 選択式 | 択一式 | 計算式 | 選択式・計算式 | |
| 通関業法 | 10問/35点 | 10問/10点 | ||
| 関税法等 | 15問/45点 | 15問/15点 | ||
| 通関実務 | ||||
| 通関書類の作成 | 2問/20点 | |||
| その他通関手続きの実務 | 5問/10点 | 5問/5点 | 5問/10点 | |
通関士試験は全てマークシート方式で回答しますが、出題形式には以下の4つの種類があります。
- 択一式:5つの選択肢から1つを選択する。該当がない場合は0とする。
- 選択式:「語群選択式」と「複数選択式」の2つがある。
- 計算式:正しい計算額を選択する。
- 申告書作成:与えられた資料から物品を分類し、申告額を計算して正しい額を選択する。
択一式では選択肢に必ずしも正しい答えがあるとは限らないため、注意が必要です。
試験科目の一部免除
通関業者の通関業務または官庁における関税その他通関に関する事務の経験が通算15年以上ある人は、通関実務と関税法等の2科目が免除になります。
また、通関業務または官庁における通関事務の経験が通算5年以上の場合は、通関実務のみが免除されます。
受験資格
通関士試験には受験資格は定められていません。
学歴・年齢・経験・性別・国籍などに関わらず、誰でも受験できます。
受験要件自体は非常に低い国家資格なので、「手に職をつけて働きたい」と考えている人に特におすすめの資格です。
受験料
通関士試験の受験手数料は3,000円となっており、収入印紙を貼った願書を郵送するか、税関の窓口に提出して支払います。
通関業者で仕事をしている人は、NACCSを使ってオンラインで願書の提出と受験料の支払いが可能です。この場合は受験料が2,900円になります。
受付期間は、例年7月下旬から8月上旬です。
※2023年は7月24日(月曜日)から8月7日(月曜日)までの2週間でした。
試験の日程
通関士試験は例年10月の第一日曜日あるいは第二日曜日に実施されます。
2023年の通関士試験は、10月1日(日曜日)に行われました。
合格の基準
合格基準は事前に発表されていないため、正確には不明となります。
ただし、一般的には全科目で6割以上の得点が合格のために必要といわれています。
通関士試験の独学合格を目指す勉強方法
通関士試験に合格するには、400時間程度の勉強時間が必要とされています。
ただし、時間をかけて勉強すればそれだけで合格する試験ではありません。特に独学で合格を目指すには、ポイントを押さえて効率的な勉強を続ける必要があります。
- インプットとアウトプットを繰り返す
- 通関業者で実務経験を積む
- 基礎を大切にする
- 過去問で出題形式に慣れる
- モチベーションを保つ工夫をする
- 効率よく学習するなら通信講座利用がオススメ
以下に詳しく解説していきます。
インプットとアウトプットを繰り返す
通関士の試験勉強を始めると、法律用語や輸出入の手続きに関する専門用語が多く出てくるため、慣れるまでは理解が難しく感じる人が多いでしょう。何度も繰り返し読み、わからない言葉はその都度意味を確認して理解することが大切です。
通関業法と関税法等は暗記が多い科目なので、自分に合った方法でインプットを繰り返し、頭に定着させる勉強がおすすめです。
通関実務の問題は、基礎知識をベースにして考える応用形式です。こうした形式の問題では多くの問題を解くアウトプットが重要です。多くの問題にあたっているうちに知識が身につき、どのようにすれば解答につながるのかがわかってきます。
通関業者で実務経験を積む
実務を経験しないで通関士試験の勉強を独学する方の場合、テキストに記載されている内容がいまひとつ実感として理解できないケースが多いものです。イメージだけで内容を理解するのは限界があるかもしれません。
通関業者の中でも貿易事務等の仕事は、通関士でなくても就業が可能です。もしチャンスがあれば通関業者の職に就き、実務経験を積みながら学習するのがおすすめです。勉強していることの理解が深くなり、学習効率を上げることにつながるでしょう。
基礎を大切にする
通関士試験の3科目のうち、通関業法と関税法等は通関士業務の基礎となる大切な知識です。暗記が多い科目ですが、ここがしっかりできていないと、通関実務の問題はできません。
試験合格には、通関実務が重要といわれていますが、基礎がしっかりしないうちから取り組んでも効果は上がらないでしょう。
学習の初期段階では、基礎になる知識を繰り返し学習し、あいまいな部分を潰しておきましょう。
応用問題を解いて、基礎になる知識に不安なところがあれば、基礎を確実に理解してから次に進むというステップを大切にすることです。
過去問で出題形式に慣れる
通関士の試験勉強では、過去問を解くことが非常に重要です。基礎的な知識が定着したら、どんどん過去問をやっていきましょう。通関士の試験では独特の出題形式があるので、慣れておく必要があります。
通関士試験の75%~80%は過去問から出題されているため、過去問を問題なく解けるようになるのが合格への近道です。
間違えた問題はできるようになるまでしっかり解説を読み、不明点がないように潰しておきましょう。
過去問は1周やって終わりではなく、何周も繰り返し解いて、出題の仕方に馴染んでおくと取り組みやすくなるでしょう。
モチベーションを保つ工夫をする
独学で試験勉強をする場合には、モチベーションを保ち続けられるかどうかで合格が決まるといっても過言ではありません。
継続するためには、毎日必ずやることを決めて、早い段階で習慣化するとよいでしょう。
毎日勉強を続けていると、疲れて休みたいときや、嫌になって止めたいと思うことがあるかもしれません。そうした状態でも何とか踏ん張って、続けていくことが重要です。
できれば身近に受験仲間を作って、励まし合いながら勉強をしていくと、モチベーションが落ちそうなときでも頑張れるでしょう。
家族がいる人は、家族に試験合格を宣言し、後に引けないように自分を追い込むというのもひとつのやり方です。
効率よく学習するなら通信講座利用がオススメ
独学で試験勉強をすることは、自分のペースでできるメリットがある反面、自分の好きな勉強に偏ってしまい効果が上がらないという方もいるでしょう。また、ペース配分の目安がないので続けているうちにだらけてしまう可能性もあります。
偏りなく効率的に学習したいという方や、勉強の目安になるものが欲しい方というにピッタリなのが「通信講座の利用」です。
通信講座では重要なポイントをまとめたテキストを使って、無駄のない学習ができます。学んだことを確認する定期的なテストもあり、通信講座を学習進度の目安にするのがおすすめです。
通信講座では、解説を読んで理解できなかった問題については、質問することもできるので、不明点を潰していくのに使うとよいでしょう。
Webや動画を活用した講座も併せて利用すれば飽きずに続けられます。また、法改正などの最新情報も送られてくるので、対策に役立ちます。利用料金もそれほどかからないため、負担なく続けられるでしょう。
通関士資格を取得するメリット
通関士の資格を取得することで、どのようなメリットがあるでしょうか。
ここでは代表的な四つのメリットを紹介します。
- 就職・転職活動に有利
- 勉強したことが実務に役立つ
- 独占業務を持っているので安定して働ける
- 受験資格がないため誰でもチャンスがある
就職・転職活動に有利
通関士の資格を取得していることで、貿易関係の仕事に就職・転職する際に有利になります。
通関士の資格を持っているということは、関税法や通関業法について理解しており、十分な知識があるということです。
通関業者はもちろん、商社などの貿易関係の仕事、航空会社や海運会社などの物流業界においても、こうした人材を求めている企業は多いでしょう。
貿易関係の業界に就職・転職したいと思っている方は、取得しておくと有利になります。
勉強したことが実務に役立つ
通関士の試験勉強で学ぶことは、通関の仕事をする人にとっては実際の業務でも役に立つ内容です。
通関業法と関税法等は通関士としての基礎となる知識で、仕事をするうえで必要になります。また、通関実務の内容も実際の業務で活かせることが多く含まれています。
通関士の資格の勉強は、単に資格を取得するための勉強ではなく、実務でも役立つものであることを頭に入れて学習を進めましょう。
独占業務を持っているので安定して働ける
通関士は、通関業務を行う専門家として税関に提出する書類を審査するための国家資格であり、通関書類の審査や通関書類への記名・押印は、通関士の独占業務と定められています。
貿易業界の中では、通関士は唯一の独占業務を持っている国家資格で、物流会社などでは通関士の存在が欠かせません。
世界的な貿易国家である日本では、今後も輸出入業務は多くあり続け、通関士の仕事が将来的になくなることはないでしょう。
上記の事情から、通関士は将来的にも安定して働ける仕事だといえます。
受験資格がないため誰でもチャンスがある
通関士の資格取得には受験資格がありません。そのため、学歴・経験・年齢・性別を問わず誰でも受験でき、合格のチャンスがあるのです。
もちろん簡単に取得できる資格ではありませんが、しっかり勉強すれば独学でも資格取得は可能です。
現状からのキャリアップを考えている方や、正社員として職を得たいと考えている方にとって、資格取得は新たな仕事の足掛かりになるかもしれません。
通関士の資格取得に興味があるのであれば、誰にでもチャンスがあり、チャレンジする価値があります。
通関士資格を取得する際の注意点
通関士の資格を取得するにあたって、事前に知っておいた方がよい注意点がいくつかあります。
通関士を目指す前に、以下の注意点を確認しておきましょう。
- 試験は年に1回のみ
- 港湾近くの勤務地が多い
- 貿易関連の仕事以外では活かしづらい
- 将来はAIとの共存が必要
試験は年に1回のみ
通関士の資格取得の試験は、年1回のみの一発勝負です。3科目ありますが、税理士試験のように科目ごとの合格というのはなく、3科目で合格できなければ、翌年も同じ試験を受けなければなりません。
試験に失敗すれば、次のチャンスが来るまで1年間も待たなければなりません。試験に臨むには、体調管理を含めて、しっかりと準備をしておく必要があります。
港湾近くの勤務地が多い
通関業者の多くは通関手続きをスムーズに行うため、税関がある港湾や空港の近くに営業所を構えています。
通関業者に勤務する通関士の勤務地は、こうした営業所になることをあらかじめ知っておいたほうがよいでしょう。
貿易関連の仕事以外では活かしづらい
通関士は、税関に提出する書類に関するスペシャリストであり、貿易に関わる業界では価値のある資格です。
ただし、専門性が非常に高いため、貿易関連以外では活かしにくいのも確かです。通関士の資格を取得するのであれば、通関業者以外では、商社や物流業者に勤務している方でないと活かせる場所がないと思っておいたほうがよいでしょう。
将来はAIとの共存が必要
通関業務は年々増加傾向にあり、20年前と比較しておよそ3倍の件数となっています。それに対して通関士の数はほとんど増えていないため、人手不足の状態が長く続いています。
その対策として、近年では手続きの簡略化が進められ、通関書類の押印も廃止される予定です。
オンラインでの手続きが増えていくことに伴って、AIの導入も進められるのではないかと予想されています。
通関業務では定型の処理も多く、AIが扱うのに適しています。手続きの簡略化とAI導入によって通関士が不要になるのではないかと危惧する声も一部で聞かれます。
しかし、いくらAIが普及したとしても通関士の仕事がなくなることはないでしょう。
通関業務ではイレギュラーな案件も多く、人が関与して確認しなければならない作業は、どうしても残ります。
依頼主とのコミュニケーションが求められるケースなどは、AIでは対応できず、通関士が扱うことになります。
将来は、通関士とAIが共存して効率的な通関業務が行われるようになると予想されています。
通関士試験の難易度まとめ
通関士は、輸出入にかかる税関の申告手続きを行う専門職です。通関書類の審査は独占業務となっており、貿易関係では唯一の国家資格として、今後も安定した仕事として活躍の場は広がっています。
通関士試験の倍率は例年10%~20%ほどで、難易度は高い試験といえます。
試験は年1回で、受験科目は通関業法・関税法等・通関実務の3科目です。一般にはあまり馴染みがない貿易関係の法律知識が必要となるため、合格までは400時間程度の学習が必要とされています。
難易度が高いとされる通関士の資格ですが、独学でも取得可能です。過去問をしっかりやるなど、試験の特性を踏まえた学習が大切です。
独学で学習するには通信講座がおすすめで、学習のペースの目安となり試験対策も用意されています。
貿易国家である日本では、今後も通関士の果たす役割は大きく、貿易に関わる仕事に興味がある方は、通関士資格の取得を検討してみるとよいのではないでしょうか。
ホワイト企業の求人を探したい人は
転職エージェントの利用がおすすめ!
独自アンケートを基に厳選!
仕事やキャリアに悩みがある人は、
キャリアバディでオンライン相談がおすすめ!
- キャリアの悩みをオンライン相談!
- 相性のいいキャリア専門家を検索可能
- 転職エージェントではないので
フラットな意見を聞ける - キャリア相談広場は無料相談可能!
キャリア相談する専門家を探す